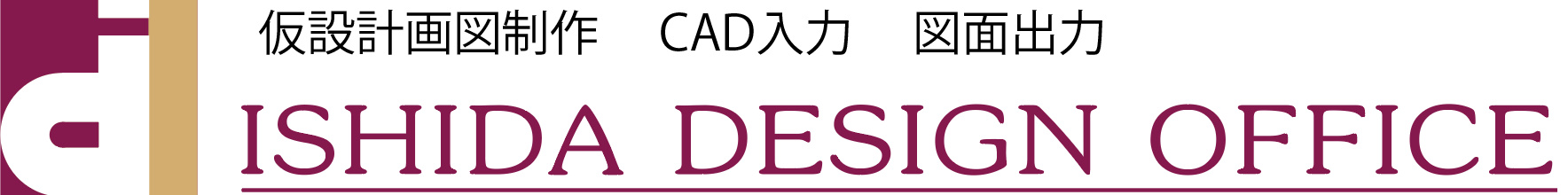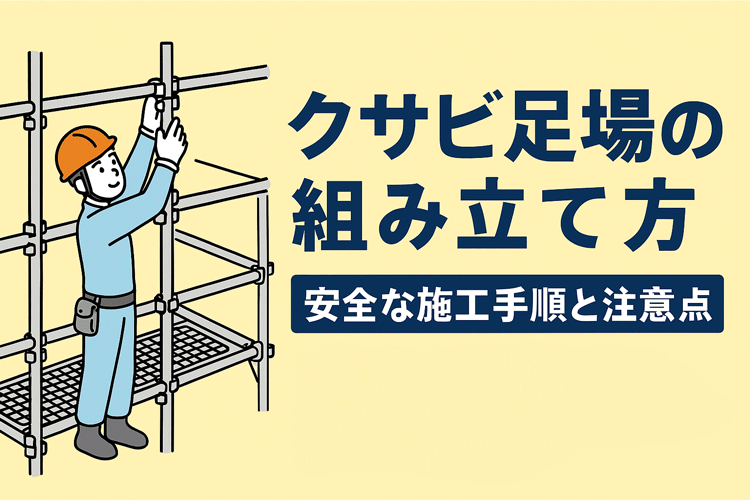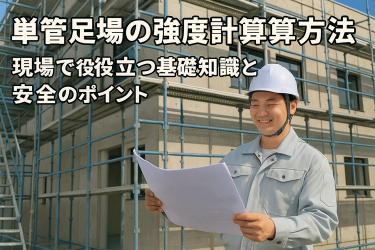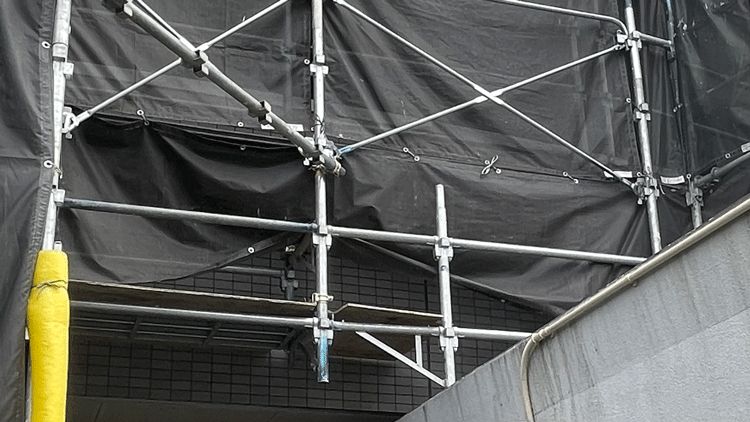
- 0.1 導入|組み立て“順番”を間違えると、全部がズレます
- 0.2 前提と用語
- 0.3 クサビ式足場の組立手順(最短で安全に組む5ステップ)
- 0.3.1 ステップ1:地盤・敷板・ジャッキベース(ここが傾くと全部がズレる)
- 0.3.2 シンワ測定 ブルーレベル Basic 300mm(マグネット付)
- 0.3.3 ステップ2:支柱建て・仮固定(最初の倒れを起こさない)
- 0.3.4 ステップ3:水平材・筋交い・先行手すり(床より先に“守り”)
- 0.3.5 無料PDF:組立チェックリスト(2025)
- 0.3.6 【無料PDF】クサビ足場 組立チェックリスト(2025年度版)
- 0.3.7 ステップ4:作業床(布板)+ロック(“落ちる床”を作らない)
- 0.3.8 ロングチップ 建設用マーキングペン 12本セット(防水・3色)
- 0.3.9 ステップ5:上層展開・壁つなぎ・昇降設備(上へ行くほど倒壊リスク)
- 0.4 組立中のNG例
- 0.5 点検・記録・教育(毎日/週次/悪天候後)
- 0.6 部材一覧・互換・仕様(先行手すり/壁つなぎの要点)
- 0.7 ケーススタディ:最上層の壁つなぎ不足→横揺れが出た
- 0.8 クサビ式足場 組立チェックリスト【無料ダウンロード】
- 0.9 よくある質問
- 0.10 まとめ 安全で再現性のあるクサビ式足場をつくるために
- 1 参考・出典リスト(省庁・規格・メーカーのみ)
導入|組み立て“順番”を間違えると、全部がズレます
現場を一周したとき、「図面は合ってるのに、なんか怖い…」って感じる瞬間ありませんか。
私はあれ、だいたい “組み立ての順番” か “壁つなぎの密度” に原因があることが多いです。
クサビ式足場は「速い・軽い・狭小に強い」反面、
先行手すりが遅れた、壁つなぎが端部で足りない——この2つだけで、墜落と倒壊の確率が一気に上がります。
この記事は、積算の話は横に置いて、組立の正解ルート(手順)+点検・記録に集中します。
監督のあなたが「現場を静かに終わらせる」ための、現場運用の形に落とし込みます。
現場で使用できるチェックリスト
現場で「確認漏れ」を減らすために、 私が実際の案件で使っている形に寄せた
無料PDF:クサビ式足場 組立チェックリスト(2025年度版) を用意しています。
「朝の5分点検」「是正→再開の流れ」 「写真・署名欄」まで含めた、現場用1枚です。
※営業メールは送りません。PDF送付のためだけに使用します(解除OK)
前提と用語
要約:この記事は“くさび緊結式足場”の組立に限定します。
まず資格配置と混用NGを押さえるだけで、事故の芽をかなり潰せます。
この記事の対象
- 対象:くさび緊結式足場(クサビ式足場)
- 想定読者:現場監督 、足場組立作業者、足場図面作成者(管理・図面確認が主戦場)
- 前提:有資格者の指導監督下で実施(作業主任者/特別教育の運用)
※実作業の詳細は、必ず現場の施工計画・元請協議・メーカー施工要領に従ってください。
用語
- 先行手すり:上層へ行く前に先に付ける手すり。ここが遅れると墜落が増えます。
- 壁つなぎ:足場と建物を固定して倒壊を止める部材。端部と最上層が弱点。
- 巾木(幅木):工具・資材の落下防止。第三者災害対策の要。
- 筋交い(斜材):揺れとねじれを止める。
- 混用禁止:メーカーが違う部材を混ぜるのは原則NG(承認条件・寸法・緊結精度がズレます)。
ここだけ強めに言います:混用は“監督側が負ける”
現場で「一見ハマるからOKでしょ」は危険です。
事故が起きたとき、責任の矢面に立ちやすいのは “組んだ人”より“OK出した側(管理側)” です。
私は見積・計画段階でここを先に潰します。混用は“最初に止める”が正解です。
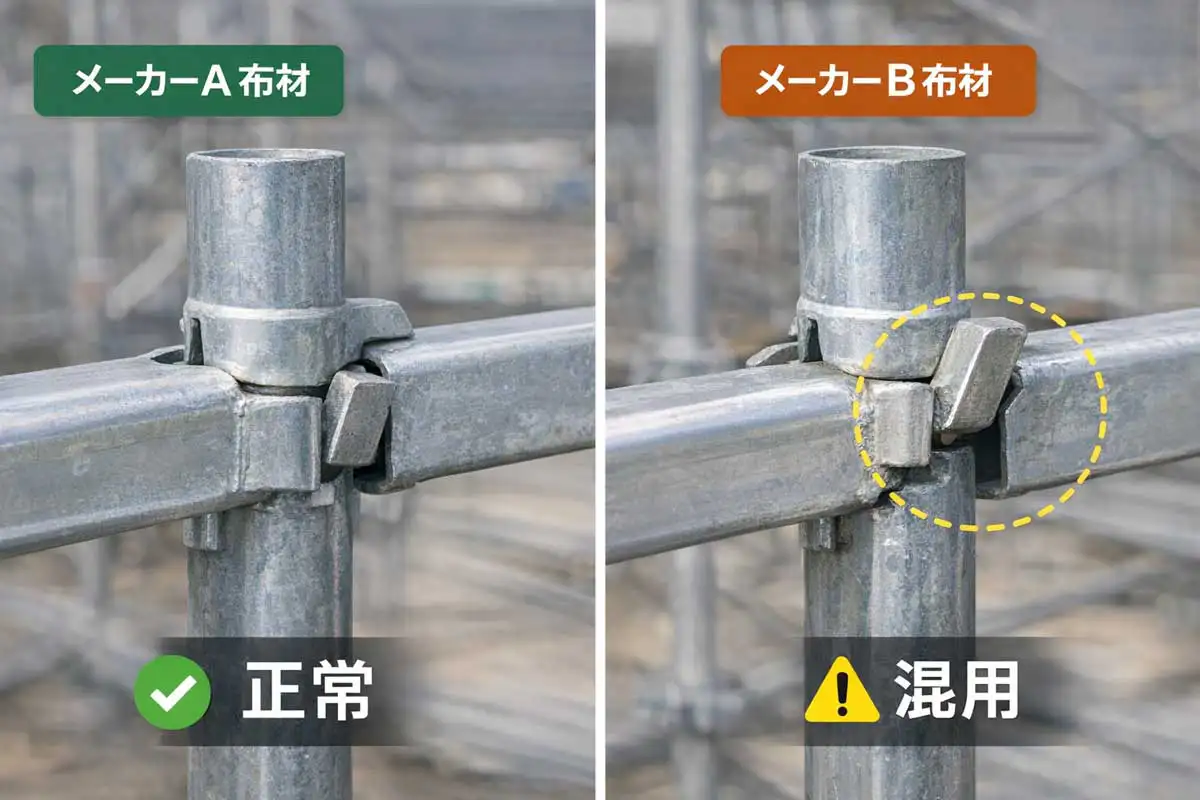
クサビ式足場の組立手順(最短で安全に組む5ステップ)
要約:組立の基本線は「地盤→支柱→ねじれ止め→先行手すり→床→上層→壁つなぎ→点検」です。
事故はだいたい「先行手すりの遅れ」か「壁つなぎ不足」に収束します。
私の現場メモ:手戻りが一番出るのは、手すりの仕様と壁つなぎピッチ を最初に握ってない時です。
ここが曖昧だと、組んだ後に全部やり直しになります。これ、現場の空気が一気に悪くなります。
ステップ1:地盤・敷板・ジャッキベース(ここが傾くと全部がズレる)
- 整地 → 敷板 → ジャッキベース据付
- 水平器で確認(沈下しそうなら敷板増し・地耐力対策)
監督のチェック(ここだけ見ればOK)
- 敷板が不足していないか(沈下が出る地盤か)
- ジャッキの据えが“効いてる”か(浮き・めり込み)
- 最初の水平が取れているか(後工程のズレの元)
- 支柱はジャッキベースから10cm以上、50cm以内を目安に設置し固定
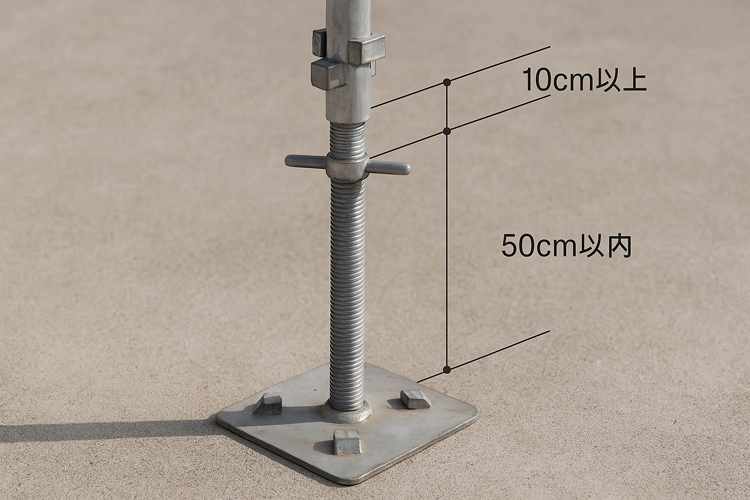

シンワ測定 ブルーレベル Basic 300mm(マグネット付)
足場工事の水平確認に最適な、マグネット付き300mm水平器。見やすい大型気泡管(クリアブルー溶液+ホワイトライン)で視認性が高く、測定面はV字溝付きでパイプ測定にも対応。ボックス型でケガキもしやすく、現場での使い勝手が良い一本です。
感度:0.5mm/m(=0.0286°)
ステップ2:支柱建て・仮固定(最初の倒れを起こさない)
- 支柱を立てたら 通り・鉛直 をその場で取る
- 支柱は2m以内の間隔で垂直に建て、根がらみ材で相互に連結
- 初期は倒れやすいので 仮筋交いで仮固定
“焦って上へ”が始まると、事故の入口です。
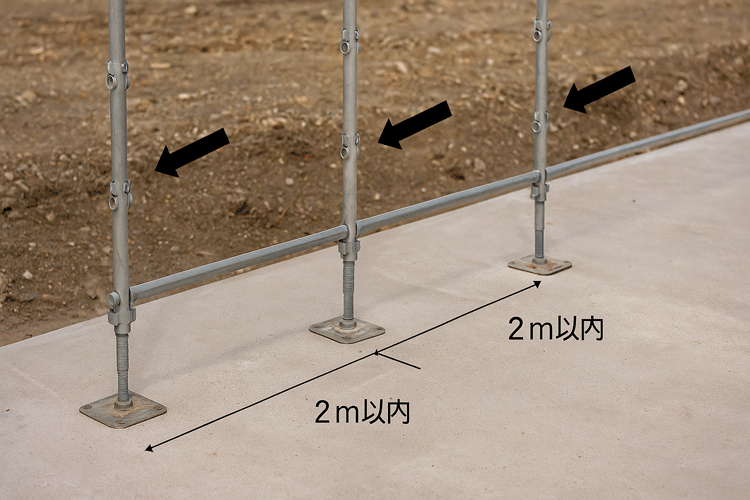
ステップ3:水平材・筋交い・先行手すり(床より先に“守り”)
- 水平材で ねじれ止め
- 筋交いで 剛性確保
- そして 手すりを前倒し(上層に進む前に付ける)
「床より先に手すり」。これだけで現場の安心感が変わります。
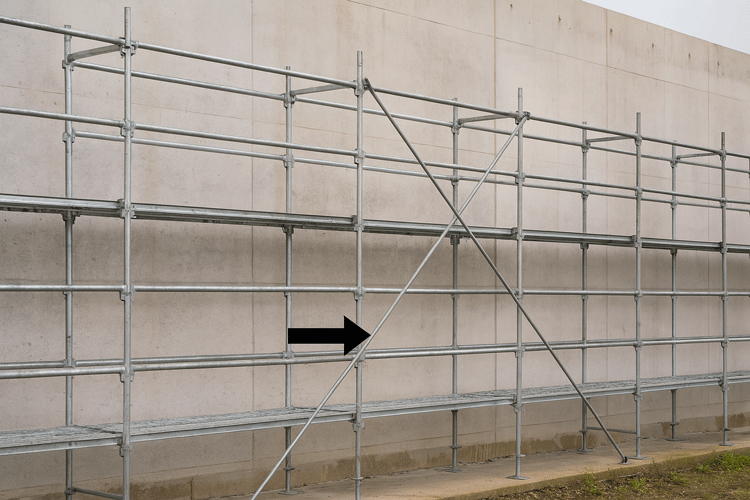
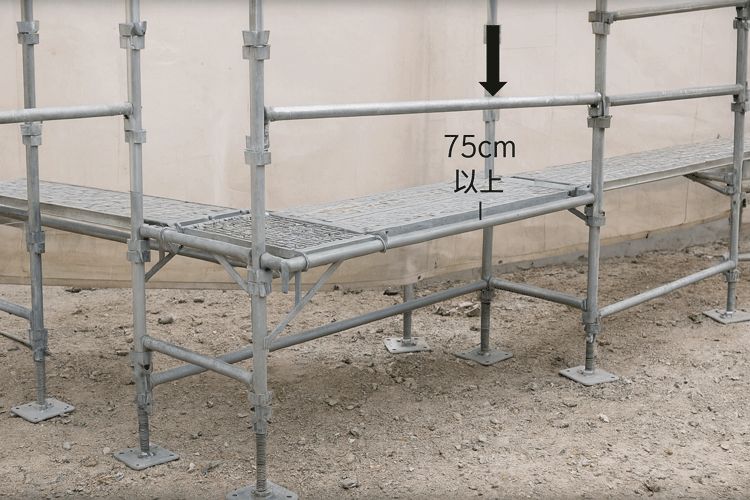
無料PDF:組立チェックリスト(2025)
無料PDF:組立チェックリスト(2025) を、この5ステップ順に合わせて作っています。
【無料PDF】クサビ足場 組立チェックリスト(2025年度版)
「確認→是正→記録→保存」を現場で回すための実務用1枚。 A4印刷/スマホ保存OK。
※営業メールなし(PDF送付のためだけに使用/いつでも解除OK)
- 点検項目を現場全員で共有できる
- 不具合→是正→再開の流れが明確
- 写真+署名記録で監査にも対応
※登録後、確認メールのボタンを押すだけでダウンロードできます
ステップ4:作業床(布板)+ロック(“落ちる床”を作らない)
- 布板設置後、ロックの掛かりを指差し確認
- 隙間・支持点不足・ガタつきは即是正
監督のSTOPライン(止める基準)
- 端が浮く/ガタつく → その場で止める(“一回だけ”が一番危ない)
- ロックが見えない → 見えるまで確認(見えない=確認してないと同じ)


ロングチップ 建設用マーキングペン 12本セット(防水・3色)
深い穴・狭い場所でも正確にマーキングできるロングチップ仕様の大工用マーカーペン。 ドアロック取り付け部、木工の下穴、設備・建設現場のマーキング作業など、 通常のペンでは届きにくい箇所で威力を発揮します。 防水・速乾性の油性インクで、屋外作業にも対応します。
- ロングチップ設計:深穴・奥まった位置でも書きやすい
- 防水・速乾:屋外・木工・建設現場向け
- 3色セット:黒・赤・青で用途別に使い分け
- 補充式:マーカーペン6本+インク6本
現場で「ペン先が届かない」「線がにじむ」ストレスを減らしたい方におすすめです。
ステップ5:上層展開・壁つなぎ・昇降設備(上へ行くほど倒壊リスク)
- 上層は 1層ずつ(同時作業を避ける)
- 壁つなぎは所定ピッチ+端部・最上層は増設
- 垂直移動は 梯子 or 階段ユニット(よじ登り禁止)
端部・最上層が“薄い”まま進んでいないか
養生(メッシュ・シート)が入った/変わった → 条件変更=再確認のトリガー
昇降が固定されているか(落下より先に「移動」が危ない)


組立中のNG例
現場で本当に出る4つに絞って、是正の流れまでセットで覚えるのが一番強いです。
よくあるNG(この4つだけ覚えてください)
| NG | 何が起きる? | 現場のサイン |
|---|---|---|
| 布板ロック未掛け | 板ズレ・落下 | 端が浮く/ガタつく |
| 手すり・中さん欠落 | 墜落 | “一瞬なら…”が地獄 |
| クサビ半掛かり | 抜け・変形・倒壊 | 叩いた音が軽い |
| 壁つなぎ不足(端部・最上層) | 横揺れ→緩み→崩れ | 風で足場が“鳴る” |
私の経験だと、ヒヤリの直前は 「足場が鳴る」「床が微妙に動く」 です。
その時点で止めれば、事故にならないことが多いです。
是正フロー(この順番だけ)
作業中止 → 責任者点検 → 是正 → 記録(写真+署名) → 再点検 → 再開
「是正した」は口頭だと残りません。
写真+チェック表+署名が、監査・労基署対応であなたを守る“盾”になります。
法的根拠と技術基準
労働安全衛生規則 第563条
→ 「作業床・手すり・開口部の点検と記録の義務」
→ 「墜落防止措置(手すり高さ85cm以上+中さん設置)」厚生労働省 改正資料(2023年)
→ 手すり高さ85cm以上+中さん必須/仮設工業会技術指針と整合。仮設工業会 技術指針(2025年版)
→ クサビ緊結部の完全固定・先行手すりの早期設置を明記。
これらの基準に従っていない状態で作業を続けると、
労働基準監督署による是正勧告・作業停止命令の対象となります。

点検・記録・教育(毎日/週次/悪天候後)
要約:点検は“おまけ”じゃなく、組立の一部です。
記録は事故が起きた時にあなたを守る「盾」になります。
日常点検(毎朝5〜10分で終わる形)
- 手すり・中さん:緩み/欠落
- 作業床:ロック、支持点、隙間
- クサビ:半掛かり、緩み
- 壁つなぎ:所定ピッチ、端部
- 通路・梯子:破損、滑り、妨げ
週次点検(構造+外装+風荷重)
メッシュシート・養生がある現場は、ここが本番です。
強風後は臨時点検を追加(“外装が変わったら条件が変わった”扱い)。
悪天候後点検(強風・豪雨・地震)
- 支柱沈下
- 布板浮き
- クサビ緩み
- 養生破損
監督の“最低限残すべき証拠セット”
- 全景写真(四方+上部)
- 要所写真(壁つなぎ/布板ロック/昇降固定)
- 点検表+署名
- 是正履歴(いつ・どこを・どう直したか)
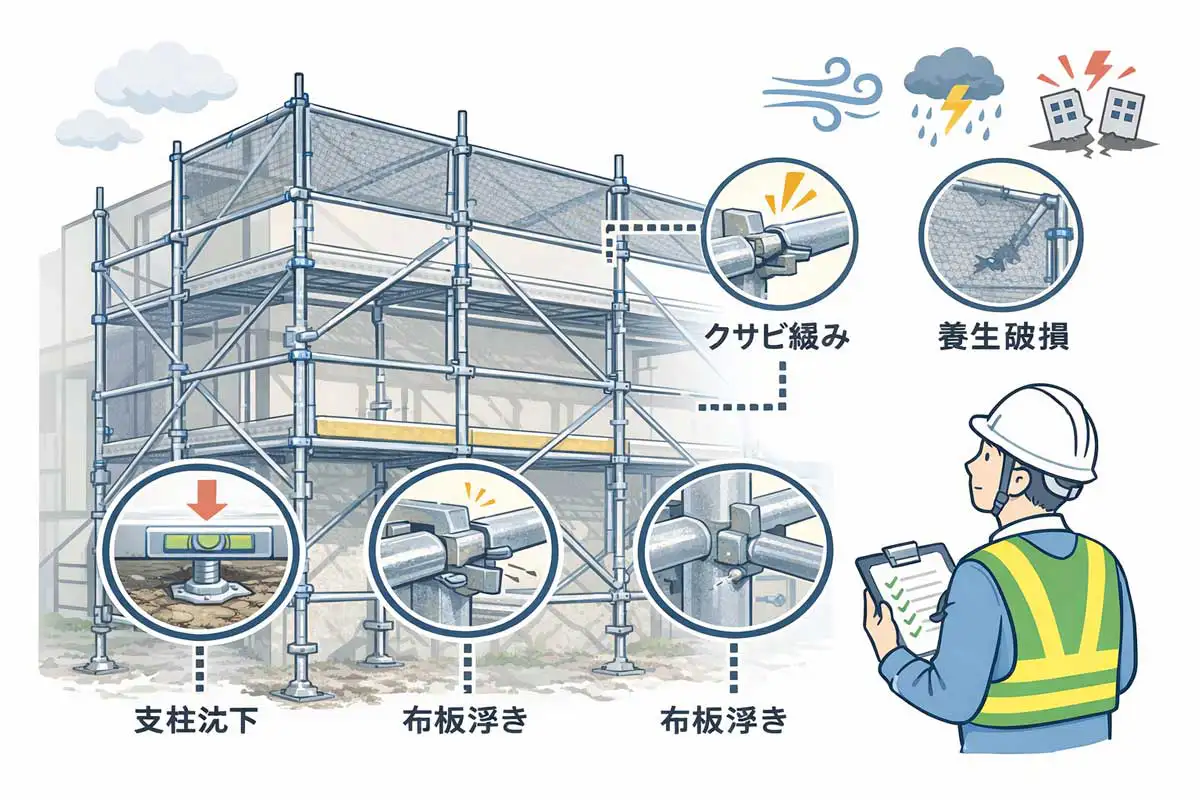

3-in-1 横長クリップボード 防水&夜間対応(ストラップ付き)
野外の足場管理・点検時に最適な、防水仕様の横長クリップボードです。雨や雪でも書類を守りながら記入でき、収納スペースに書類や小物をまとめて持ち運べます。
低照度ではスマホのライト(フラッシュ)を収納部で活用して手元を照らす使い方も可能。調節可能なストラップ付きで両手を空けやすく、巡回・検査・屋外作業に向きます。
厚手PVC素材で耐久性に配慮され、A4書類の管理にも便利です。
部材一覧・互換・仕様(先行手すり/壁つなぎの要点)
要約:部材は“同一システム”で揃えるのが基本です。
先行手すりと壁つなぎは、設計段階で握っておくほど手戻りが減ります。
最低限押さえる部材(管理側のチェック用)
| 部材 | 役割 | 監督側のチェック |
|---|---|---|
| 支柱・布材 | 骨組み | 変形・亀裂・摩耗 |
| 筋交い | 揺れ止め | 欠落・緩み |
| 先行手すり | 墜落防止 | 認定・適合品/混用NG |
| 壁つなぎ | 倒壊防止 | 端部・最上層の密度 |
| 布板(床) | 作業床 | ロック・隙間・支持点 |
| 巾木・養生 | 落下防止 | 外周の欠落 |
佐藤さん向け実務:私は見積・計画段階で、
「先行手すりは何を使う?」→「壁つなぎはどのピッチ?」 を先に確定させます。
ここが決まると、現場が静かになります(ムダな議論が減る)。
ケーススタディ:最上層の壁つなぎ不足→横揺れが出た
早期に気づけば、倒壊や墜落の手前で止められます。
- 現象:強風時に上層が横揺れ → クサビが緩む → 床に隙間
- 原因:端部・最上層の壁つなぎが薄い/養生条件の変更が共有されていない
- 是正:壁つなぎ増設+筋交い見直し+全緊結部の再点検
- 再発防止:「養生変更=構造再確認のトリガー」 をルール化
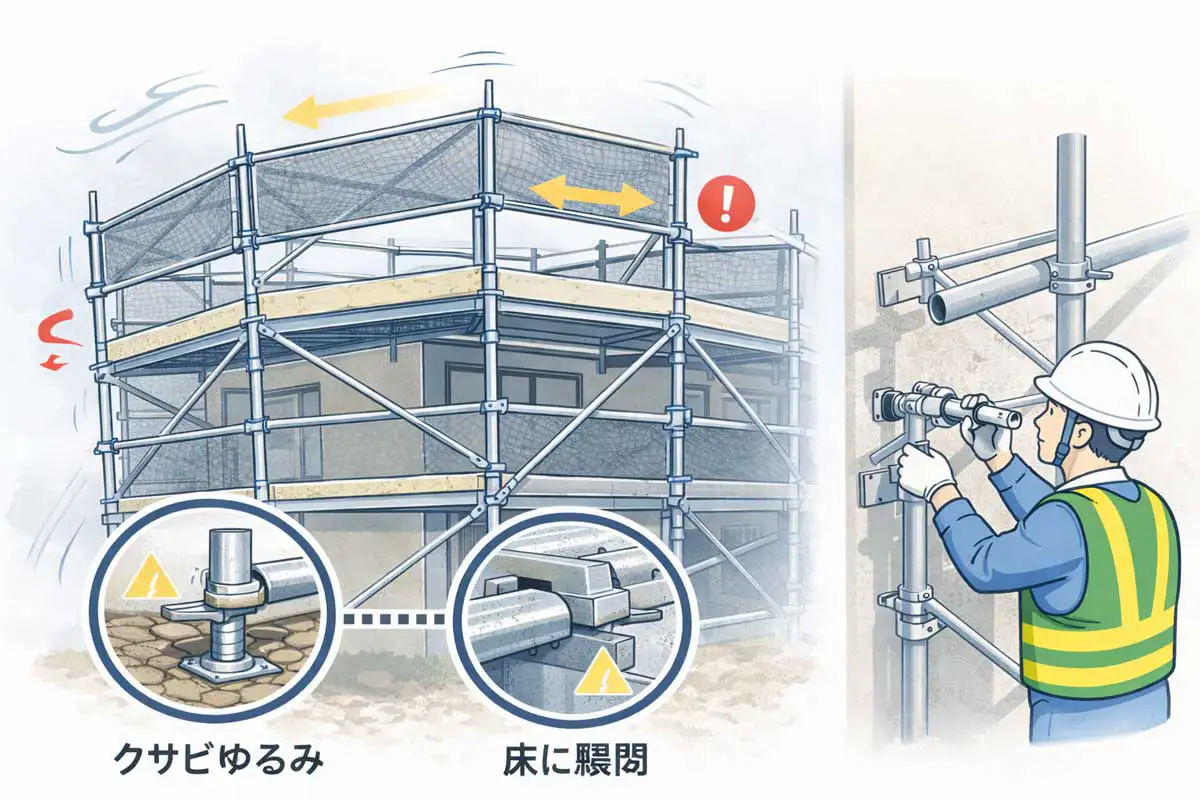
クサビ式足場 組立チェックリスト【無料ダウンロード】
PDFの内容(抜粋)
| 確認項目 | 主なチェック内容 |
|---|---|
| ジャッキベース・地盤 | 敷板・水平確認・沈下なし |
| 手すり・中さん・巾木 | 高さ85cm以上/巾木10cm以上 |
| 壁つなぎ | 9m×6m以内(実務5.0×5.5m標準) |
| 安全帯・ハーネス | 常時フルハーネス使用 |
| 記録・保存 | 写真+署名を残し3年間保存 |
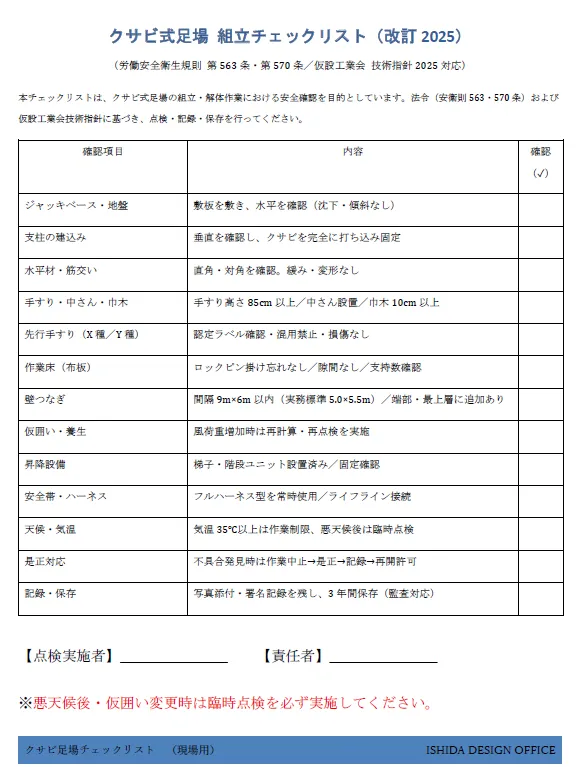
(※PDFはA4サイズで印刷し、現場でそのまま使えます)
現場でそのまま使える「クサビ足場組立チェックリスト(2025年度版)」無料PDF
現場で事故ゼロを目指すには、
「点検と記録を習慣化すること」 が何より重要です。
多くのヒヤリ・ハットは、
「確認漏れ」「記録不足」といった 小さな油断 から起きています。
仮設工業会 技術指針(2025年改訂) と
労働安全衛生規則(第563条・第570条) に基づき、
現場でそのまま使える
「クサビ式足場 組立チェックリスト(2025年度版)」 を作成しました。
このチェックリスト1枚で、
- 作業前の点検項目を現場全員で共有
- 不具合発見 → 是正 → 再開許可までの流れを明確化
- 写真+署名記録で監査・是正対応にもそのまま使用可能
現場監督・職長・足場組立業者にとって、
「自社の安全管理を見える化する必須ツール」 です。
メールアドレス登録後、確認メールのボタンを押すだけで受け取れます。
営業メールは送りません。PDFを確実にお届けするためだけに使用します(いつでも解除OK)。
- 「確認 → 是正 → 記録 → 保存」までを一連の点検として回せる
- 悪天候後・変更後の“点検理由”が書きやすい
- A4印刷/スマホ保存どちらも対応
※クリック計測はGA4イベント「download」を想定(GTM/設計に合わせて調整OK)
よくある質問
まとめ 安全で再現性のあるクサビ式足場をつくるために
2,事故は2つに収束:先行手すりの遅れ/壁つなぎ不足(端部・最上層)
3,NGは4つだけ徹底:布板ロック、手すり欠落、半掛かり、壁つなぎ不足
4,点検と記録が“盾”:写真+点検表+署名+是正履歴
5,チェック表で仕組みにする:安全と段取りが同時に回り出す
最後にひとこと。
現場監督って、トラブルが起きないほど評価されにくい仕事なんですよね。
でも私は、事故ゼロで終わった現場の静けさが一番好きです。
この記事とチェックリストが、佐藤さんの現場で「ムダな手戻り」を減らして、安全とコスト削減と段取りのスムーズさにつながれば本当に嬉しいです。
また引っかかったら、いつでもこの記事に戻ってきてください。私は“味方側”で書いています。

参考・出典リスト(省庁・規格・メーカーのみ)
- 労働安全衛生法/労働安全衛生規則(墜落防止・点検記録 等)
- 一般社団法人 仮設工業会:くさび緊結式足場の技術資料・安全指針(最新版)
- 主要メーカーのシステム承認・適合証明・施工要領書(混用禁止・仕様確認)
※最終更新日:2025/12/27
【更新履歴】
- 2025/12/27:構成を「組立手順+点検」に集中、積算パートを分離
- 2025/11/10:点検・記録の項目を追加
- 2025/08/01:先行手すり/壁つなぎの注意点を追記
この記事の執筆者/監修
👤この記事の執筆者/監修
ISHIDA DESIGN OFFICE
代表 I.D.O(仮設設計技術者/足場組立作業主任者)
• 建設業歴30年以上、仮設設計・点検・講義実績多数・仮設設計技術者
• 厚労省・仮設工業会の最新基準に基づき執筆
仮設設計・CAD作図・構造チェックのご依頼はこちら:
ISHIDA DESIGN OFFICE 公式サイト